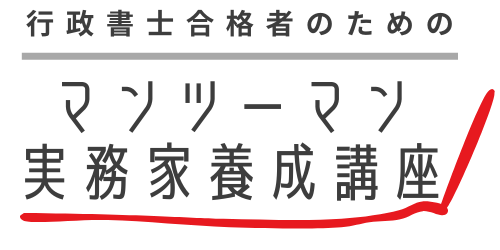受講者から頂いた感想の一部をご紹介します。
マンツーマン方式のおかげで自分にとっての「開業に向けて準備すべきこと」が整理できました。1年後の開業に向けて、専門分野の精度アップに邁進します!今後ともどうぞよろしくお願いします。
30代 会社員・男性
本を読むだけでは知ることのできないお話をたくさん伺うことができました。また柔和な物腰で一受講生に懇切丁寧に接してくださり感激しました。開業へ向けて気分一新!準備を重ねて行きます!
40代 無職・女性
お世辞でなく、講座に参加したおかげで「自分のやるべきこと」が見えてきました。明日、相談されてもうろたえないように、ぬかりなく準備をします!今後ともよろしくお願いします。
20代 アルバイト・男性
開業直後に高難易度の案件を受任してしまって「大丈夫かな・・・」と不安でいっぱいでしたが、講師のアドバイスのおかげで無事にやり遂げることができました。
依頼者から「本当にありがとうございます!」と感謝の言葉を頂いた瞬間、「この世界に飛び込んでよかった」と心底思えました。これもしっかりと準備した賜物です。本当にありがとうございます!
30代 開業者・女性
専門分野の選択に悩んでいましたが、講師と話しているうちに自分に潜んでいた「専門性」を発見できました。1年後の早期退職後の開業を目指して実務の習得と営業に邁進します。本当にありがとうございます!
50代 会社員・男性
遺産分割のご相談の初面談で業界水準を大きく上回る「満足行く報酬」で受任できました。講師から面談の要点を聞いておいて本当によかったです。
40代 開業者・女性